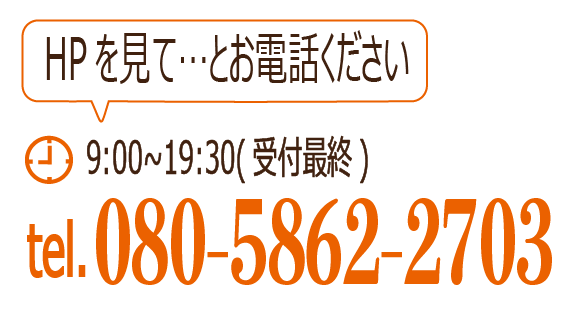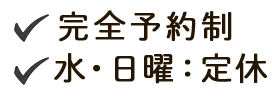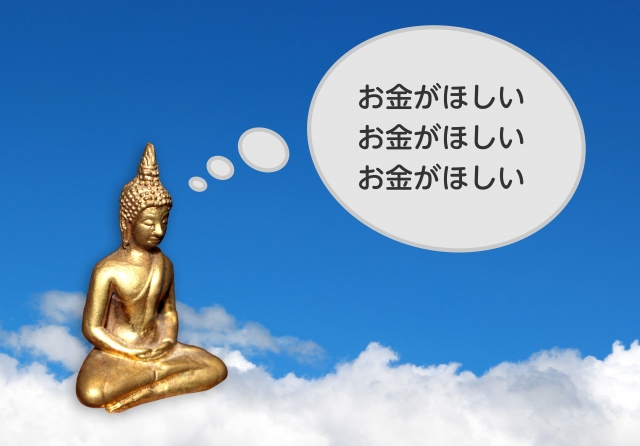
『あの世とこの世の受けとめ方 ―疲れているあなたへの支え―』 恵林寺住職 古川周賢 老大使
まず、住職の古川さまは、東大の博士(哲学)ご出身で、その後仏門の修行に入られています。これってすごいことですよね
はじめに あの世を信じるか?という統計データをご紹介頂きました。1980年頃と、2010年頃の比較だったと思います(年代は不正確)
特徴は、近年の20代、30代はあの世を信じていいる人が非常に多くなっている。高齢者では変わらない状況でした。
宗教を信じない世代が、逆にあの世を信じている・・・・・面白い傾向です
そもそもあの世とは 極楽とか、地獄とかおういうイメージですが、仏教でいう極楽浄土は宇宙の果ての果ての果ての遠くにあるようであす
そしてそこには阿弥陀如来がおられるところ
仏教の開祖である釈尊は あの世があるとは答えていません。「死後は?」の問いには 無言だったそうです。その理由は・・・・
私たち人は、身体に毒の矢が刺さっているような状態で、優先されるのは、この状態を手当てすること
「死んだらどうなるの?」という質問に答えても、手当の役には立ちません。
生きていく中で、「生・老・病・死」の苦しみに直面し、悲しみ、嘆き、憂いの悩みに苛まれています
死後より現在 眼の前にある苦しみに向き合うべきという理由です
また、道元禅師は 生きることと死ぬことを1つのことと考えよと言われています。
精一杯生きることに向き合えば、生命の儚さ(はかなさ)、脆さに突き当たります
死ぬことを考えるなら、どのように生きることを全うするか そして死を迎えるか まず生を真摯に考えること
命は、頂いたものです、ありがとうございますと丁寧に扱うことが必要です。
生きていく中では 四苦八苦があり、それらを乗り越えていく必要あります。それこそが修行となります
そうは言っても、乗り越えられそうにない苦もあります。今乗り越えられそにないものは 逃げればいい
心の準備ができて、力がついたとき再度向かい合えばいいのです
うまく行かないときは、学べばいい、拗ねてもダメ。決意、覚悟がないと変わりません
覚えているのは こんな感じです
少しは参考になればいいなぁと思い、ご紹介しました。
四苦八苦という言葉も仏教用語だったんですね
年に2回、コンパスがなくても正確に西方を向くことができる日が春分の日、秋分の日
この日は真西に太陽が沈みます、西方極楽浄土はその遥か彼方にあるようです
今日は6月4日です。今日のご利行動は経済を見直すです。現状の収入、市場はどうなっているか、今一度確認しましょう
今日のご利益フードはサクランボです。南アルプスですは、サクランボ狩りも始まっています
今日も元気でよい日になりますように、修行していきましょう!!